宝暦3年(1753)広島国泰寺十一世・笑堂和尚が広島藩より扶持を得て、木ノ庄町木門田に隠居し、三原宗光寺末の西宝寺に住していた。
宝暦9年(1759)栗原村樋口屋又兵衛の寄進により現在地に移転し、笑堂和尚を開山
としました。
済法寺七世喝童和尚の代・享和年間、尾道の問屋などの喜捨により裏山巨岩の中央最も高い所に釈迦如来像を刻し、そのほか17の巨岩転石に正法護持の聖者達、十六羅漢像や従者、阿羅漢像など総数23面・26尊者を半肉彫りに刻し、山全体を曼荼羅図に仕立てられた摩崖仏は非常に有名です。
第九世・物外不遷和尚は「げんこつ和尚」の別名を持つ傑僧として名高く、柔術不遷流の開祖として3千人の弟子を抱え、幕末勤王僧として活躍しました。
怪力無双、碁盤の横腹を拳骨でなぐると大きく碁盤が引っ込んだといいます。また、京都の新撰組の道場で近藤勇がくり出す槍を鍋の蓋で取り押さえたという逸話も残っています。
俳句にも長け多くの句を残す文武両道の傑僧で、寺には物外和尚ゆかりの品々が保存されています。
   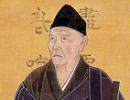
|